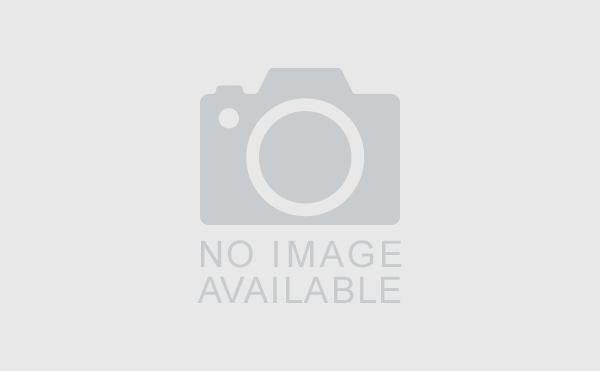リレーメッセージ第7回:滋賀県立総合病院 N・Hさん

滋賀県は広く、ST同士が交流できる機会が多くありません。
「リレーメッセージ」と題し、県下STに自由にお話いただく場を作る事で、滋賀県STってこんな感じなんだ!と繋がる場を企画しました。「よもやま話」が集まり、滋賀県下の現在そして未来のSTへのメッセージとなることを期待しています。
第7回目は、滋賀県立総合病院のN・Hさんにお願いしました。
聴覚領域のお話を頂戴できました。
下記よりご覧ください。
リレーメッセージ:第7回
この3年間を振り返って
私は言語聴覚士として働き始めて今年の4月で4年目を迎えました。四年制大学を卒業後、社会人経験を9年、その後専門学校で2年間勉強し、現在の病院に就職しました。企業で働いていたころはパソコン作業が中心の仕事だったので、「もっと人と関わる仕事がしたい」という思いがあり、様々な資格・職業を探している中で言語聴覚士を知りました。過去の自分が、現在病院で働いている自分の姿を見たら、きっと驚くと思います。
さて、私は耳鼻いんこう科に所属し、成人の聴覚障害領域の言語聴覚士として働いています。補聴器外来での補聴器適合検査、人工内耳の調整(マッピング)・リハビリ、補聴器装用者の聞こえのリハビリを行っています。
専門学校2年生になり就職活動を始めた当初は、回復期?急性期?どの領域で働きたいか全く決まっていませんでした。専門学校に在籍していた2020年〜2022年は、コロナが流行し始めた最盛期の時期でした。そのため、病院での臨床実習は次々と校内実習へ変更となり、実際に病院で働くイメージを持てませんでした。その時に、企業で働いていた頃に出会った難聴の同僚(Aさん)のことを思い出しました。Aさんは当時50代後半、幼少期から難聴で聴力は90dB以上、補聴器を装用していましたが音声のみのコミュニケーションは難しく、手話ができる職員とペアとなり、手話と筆談を交えながら仕事をしていました。専門学校で学ぶ中で聴覚障害に興味はありましたが、改めてAさんのことを思い出したときに、「私は耳が聞こえることを当たり前だと思い生活してきたけど、聞こえない・聞こえにくいとはどのような世界なのだろう」「今までAさんはどうやって言葉を学び、コミュニケーションを取ってきたのだろう」「日常生活や仕事で苦労はなかったのだろうか」など、様々な思いがわいてきました。そして、難聴の患者さんに寄り添う言語聴覚士になりたいと思い、聴覚障害領域への就職を決めました。
しかし、いざ就職してみると、難聴の患者さんとどのようにコミュニケーションを取ったらいいかわかりませんでした。私が今まで出会ったことがある難聴者はAさんしかいなかったのです。そのため就職当初は、患者さんにとりあえず大きな声で話しかけていたと思います。今思えば患者さんにとっては聞き取りづらい話し方をしていたのではないかと反省しています。また、聴覚障害だけではないと思いますが、患者さんは一人一人違います。難聴は外見からはわかりづらい障害のうえ、聞こえにくさも様々です。補聴器・人工内耳を装用しているから、100%聞こえるわけではありません。専門学校で学んだはずなのに、いざ臨床に入るとそのことを理解できていない自分にガックリすることもありました。職場の先輩たちからのアドバイスや、先輩たちがどのように患者さんと接しているかを観察する中で、私も少しずつ難聴の患者さんとの会話に慣れていきました。
また、臨床の中で、難聴者自身の努力や工夫だけではなく、会話の相手、職場や家族、周りの方達の協力も必要ということを学びました。話し手の話し方の工夫(ゆっくりはっきり話す、短い言葉で伝える、こちらに注目してから話し始めるなど)や環境によって聞き取りやすさは変わります。そのことをご本人・ご家族に伝えることも言語聴覚士の大切な役割だと思います。
人工内耳のマッピング後や聞こえのリハビリ後に、「この調整でよかったのか…」「もっとこういうリハビリ、カウンセリングができたのではないか…」と振り返る毎日です。仕事で悩んだ時に、卒業した専門学校の先生に相談したことがありました。その時先生から、「その人の聞こえを想像して、考えることは大切。だけど、その人の聞こえ方を全て把握することはできないし、わからない。だから患者さんから教えてもらうことも必要なんだよ」というアドバイスをいただきました。臨床に入りはじめた頃は、「患者さんの聞こえのために、自分で何もかもできないといけない」と思っていました。しかし、先生のアドバイスから、「その人の聞こえはその人(患者さん)にしかわからない」ということに気づき、リハビリをするうえで患者さんに教えてもらうことも大切であると思うようになりました。特に人工内耳の患者さんには、日常生活での聞こえ方や困りごとをメモに書いてもらったり、リハビリの時に伝えてもらうようお願いしています。しかし、患者さんに教えてもらうだけでは人工内耳の調整やリハビリはできません。患者さんからの訴えに応えられるよう、様々な知識が必要です。そのためには日々の勉強が必要で、言語聴覚士にはゴールがないと痛感しています。
これからも様々な難聴の患者さんと出会うと思います。患者さんが補聴器や人工内耳を活用して家族や友人とより良いコミュニケーションを取れるよう、患者さんと一緒に聞こえをつくっていく言語聴覚士でありたいと思っています。 今回はこのような機会をいただき、また最後まで読んでくださり、ありがとうございました。